ラマルシュ=ヴァデルの頭のなかにはアイデアが溢れている。そのインスピレーション源は非常に多様だ。科学から文学、ダンス、政治、歴史、哲学、そしてアート。
美術評論家の父とアーティストの母のあいだに生まれた彼女は、フランス・ブルターニュ地方の辺鄙な場所で育ち、絵を描くこと、考えること、文章を書くこと、誰かと話すことばかりしていたという幼年時代を過ごす。型破りで独立精神にあふれた両親は数多くのアーティストやアートコレクター、作家をよく家に招き、ラマルシュ=ヴァデルは両親と客人たちとの夜通し続くよくわからない会話を、テーブルの下に隠れてずっと聞いていた。そしてそのうち彼女は詩や、未完結の多くの小説を書き始めた。さらに劇作品も企画し、みんなを無理やり集めて劇を見てもらっていた。みんなで集まり楽しむこと、そしてものづくりをすることは、私が小さいときから自然と周りにあったものと彼女は語る。
その後、パリのソルボンヌ大学で政治学、歴史、美術史を学び、16歳からギャラリーやアート施設などでのインターンシップの経験を積む。初めて彼女が手がけたキュレーションは必要に迫られて企画したものだった。彼女は友人たちとパリで、場所もお金もスポンサーもないところから、空き地を見つけ、セッティングし、企画を実現した。ベルリンに移り、アンダーグラウンドのアートプロジェクトを次々と成功させ、現在はパリのパレ・ド・トーキョーのキュレーターとして活動している。
今回のThe Fifth Senseのための作品では、ラマルシュ=ヴァデルはかねてより関心を抱いているという実験的なキュレーションと、洗練された立派な展覧会というアイデアをひとつにし、〈映像の展覧会〉というかたちで提示した。その映像はCHANEL Nº5 L’EAUの持つ革新的なパワーにインスパイアされており、6名の女性アーティストがフィーチャーされている。儚さ、身体、感情、魅力、再生という5つのテーマを掘り下げ、観る者に空間と時間、そして感情と変形を体感させる作品だ。流れるような映像は物理的な空間から解き放たれ、香水と同じように複数の層やノート(香り立ち)によって構成された展覧会、アートを見せてくれる。インスタレーションやダンス、立体作品、写真、朗読、音楽を通して、ラマルシュ=ヴァデルは「もし香りが語りかけてくるとしたら?」という問いを私たちに投げかける。
もし香りが語りかけてくるとしたら?

現在の仕事や世界観に、幼年時代の影響は反映されていますか?何世代にもわたって受け継がれてきた一族の文化、その精神は今でも私のなかに息づいています。つまり世間一般の価値観や考え方を疑うということ、アートとは何かを常に考えること、そしてアート活動をする時と場所を決める人を支援するということです。私たちは世界で起こるすべてのことを語りあっていました。芸術のこと、人間のこと、政治問題、社会問題…。自分を取り巻くすべてのものから私の価値観が形成されたんです。子どもの頃は物理的に非常に孤立した環境にいました。どこまでも続くような野原に囲まれ、天候も悪い土地に暮らしていた。しかしその環境こそが私の回復力を鍛えたし、わくわくするような想像力を育む必要性をもたらしてくれたのです。幼年時代にはとても貴重なものを得たと思います。それは未知のものを疑いじっくり吟味するという姿勢です。どんなに安全性が保証されている考え方よりも、そういう思考をするほうが私個人としては確かだと思っています。
あなたにとってのアートの意味を教えてください。アートとは何か、ということについて、私はひとつの決まった見方をもっているわけではありませんし、これからもそうであればいいと思っています。ただ、より広い世界、より広い視点のなかに置かれたときにアートがどういう存在であるか、芸術やクリエーションは今どのような存在感を有しているか、それらは対話や自己認識のきっかけになれるのだろうか、そういうことを考えています。私の一族の半分は、戦争難民として移住し、その立場であるからこそ受ける苦しみを耐えてきました。一度そのように人間性を喪失した感覚を経験したならば、人間としての自分をどのように保てばいいのか、そんなことを考えざるを得ないでしょう。きっと、「かくあるべき」と断言するような危険な規範から離れたあらゆる〈ものづくり〉が、その問いに対するひとつの答えになるはずです。
アートとは何かということについて、ひとつの決まった見方をもっているわけではないし、これからもそうであればいい


香りは、時間と空間を超える実体のない物質。恒久不変でありながら変わりやすい、そんな美しいパラドックスを内包した存在
キュレーションを始めた経緯について教えてください。それは2007~2009年にかけてのフランスの政治状況とリンクしていました。当時は対政府の学生運動が非常に盛んでした。政府が学生や教育機関を軽んじ、研究水準を貶めるような各種教育改革を推進していたのです。3年ものあいだ私はほぼ授業を受けられませんでしたし、教育現場は完全に麻痺状態でした。そこで友人たちと展覧会を企画し、夜集まって自分たちにどんなことができるか、何時間も話しあう日々を過ごしました。政府の改革案のおかげで私たちは自らの将来について信じられなくなっていました。だからその話しあいはやがて、自分たちには何ができるか、構築されつつあるシステムに対しどんな代替案を提示できるか、そういう内容になっていきました。
初期の展覧会はどんな内容になりましたか?正直なところ、すばらしい展覧会を実現したというよりはとにかく気持ちだけでかたちにした、という感じでしたね。アイデアや決意は強かったのですが、若いアーティストたちを宣伝するための資金も場所もスポンサーもなかった。そのため有名な場所はあきらめて、森のなかで開催することにしました。そこでパーティーやミーティングを行うことにしたんです。友人やアーティストだけでなく参加したい人は誰でも誘って、パリ郊外の森で5~6時間。場所を選び、設営し、その場所を使うのですが、それがどんな場所であれ、数時間後にはすべて撤去します。そういう仕組みにしたことにより、「私たちには建物も組織も必要ない、それよりも重要なのはエネルギー、そして人々の気持ちがシンクロすることなんだ」と理解できました。私たちは共にひとつのプロジェクトを実行する。でもそのプロジェクトのゴールは瞬間的にしか存在しないのです。私たちの危なっかしさが美しく力強い表現のツールとなったのだと思います。それを深め、転じて自分たちの強みにしたのです。さらにそれは、幻滅と戦う術ともなりました。
アートとは何か、文化とは何かということを、みんなで考え話しあうことが、アートの世界に身を置くすべての人間の義務だと思う
その考え方はこれまで手がけてきた仕事にも反映されているのでしょうか?そうですね。現在ではさまざまな規模のプロジェクトを手がけていますが、あらゆるスケールの展覧会を行なうことは私にとっては不可欠です。たとえば今でも一晩だけ私の住居で展覧会を行なったりします。それは、ほんのわずかな時間にどんな物事が起こるのか、それをアーティストに想像してほしいからです。私はバランスを欲しているのでしょう。非常にパブリックな内容のものと、情報を公開せず、形跡も何も残さないけれど、参加した人の記憶のなかに残るようなもの、そのふたつのバランスです。5時間だけの〈儀式〉を創造してみてほしい、とアーティストに依頼することから始まるプロジェクトは、より大きなプロジェクトを手がけるのと同じくらいおもしろいですね。そういうプロジェクトはいろんな表現が試せ、時間や空間、存在をキャンバスのように使える実験室のようなものです。
『Just a Second』について教えてください。私は香りのもつパワーというものに関心を抱いていました。想像を超える、計り知れないパワーです。香りは、時間と空間を超える実体のない物質だと私は考えています。恒久不変でありながら変わりやすい、そんなパラドックスを内包した存在。香りによって私たちは世界を知ることも、我を忘れることも、自分自身と出会うことも、他人と出会うことも、自己の状態を変化させることも、そして文字通り〈生きている〉と実感することもできます。芸術作品も香りと同じように、見えないものをとらえるためのひとつの手段といえるでしょう。作品は、思考や感情、自己投影、夢をかたちにするのです。現状に対する美しく力強い抵抗であり、過去・現在・未来の経験を通した私たち自身の改革なのです。「君たちやさしい人々よ 君たちのことなど意に介さない風のそよぎのなかへ立て」。これは詩人ライナー・マリア・リルケ(Rainer Maria Rilke)の詩の一節です。この言葉には、人間が、実態のない周囲のあらゆるちからによって永久にかたちを変えられていくということが端的に表されていると思います。
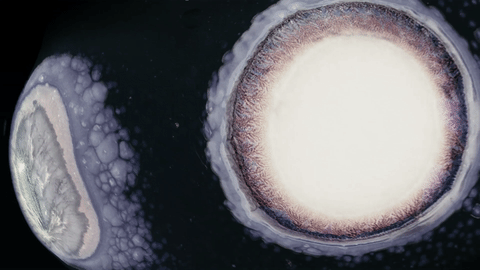
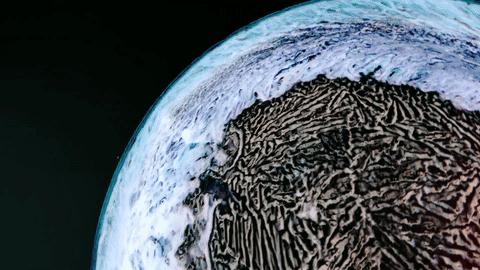
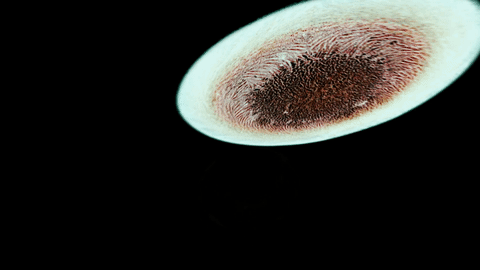
あなたの香りの世界への探求を具現化するものとして選ばれた5作品について、説明をお願いします。この5作品は、ナレーションとオリジナルのサウンドトラックでつながっています。まずブリジット・ポーク(Bridget Polk)の『Promises of the Ephemeral』。目に見えない物質のちからと、壊れやすさ、そして時間という概念を見つめる作品です。ポークはバランスをとりながら石を重ねますが、どれくらいの時間、その状態をキープできるのかは誰にもわからない。つかの間にしか存在しない立体作品は魔法のようです。糊もいかなる道具も使用していません。見えざる力が作品をかたちづくり、そして完成したと思った作品はそのあと崩れ落ちて消えてしまいます。
エリザベス・ジャガー(Elizabeth Jaeger)の作品は内部の変化と変質を表現しています。私というものは、1枚の皮、ひとつの身体のなかに収められた数々の自己なのだ、というコンセプトです。そのすべてが自分であり、異なる自己が表出するときにカタルシスを感じる。〈本当の自分〉〈過去の自分〉〈理想の自分〉を自由に行き来するのです。私というのはひとつの固定したアイデンティティではなく、もっと流動的なものだと教えてくれます。
ザラ・シューンフェルト(Sarah Schönfeld)が見せてくれるのはさまざまなホルモンの姿。それらがもたらす感情や気持ちは知ってはいても、ホルモン自体がどんなかたちをしているかは知りませんよね。希望、悲しみ、愛、魅力、欲望を司るホルモン。自己の内側の地図を、ミクロの世界なのか宇宙の世界なのかわからなくなる、そんなスケール感を楽しみながら明らかにしていきます。

マルグリット・ユモー(Marguerite Humeau)の『What Happened?』では、私たちがたどり着けない人間の大きな謎を、さまざまな対話をもとに理解しようと試みています。彼女はできる限り多くの研究者や科学者たちと話し、その結果、誰も答えを知らないというところまで研究を深めました。そしてすべてが単なる仮説であり、いかなる手がかりもないということを認めるほかないことが明らかになったのです。この作品は、〈魅力〉や〈欲望〉、〈所有〉という感覚を創出した最初の生物についての仮説に基づいた作品です。香りは誰かの存在を識別するためのもの、そして魅力を感じさせるものです。それは肌の問題でもあります。皮膚が放出している物質そのものが香りですから。
サウンドトラックは日本出身のDJ/作曲家のPowderに依頼しました。彼女は非常に才能のあるDJです。サウンドトラックも、ビジュアルと同じくらいに重要です。それぞれの作品のリズムと特徴に合うようにオリジナルの音を作ってもらいました。
もうひとつ大事なのは香りの声。作品と〈ダンス〉をしているような、私たちのヴィジョンとじゃれているような。観る者の目に映るイメージのなかを案内しながら、私たちの心のなかにまた新しいイメージをかたちづくります。香りという感覚が、私たちといっしょに遊んでいるようなコンセプトです。この遊び心のある声は、どこにでも存在していて、香りがどう作用しどう反応するか、どう創造しどう消えるか、そういうことを教えてくれるのです。
Episode 6
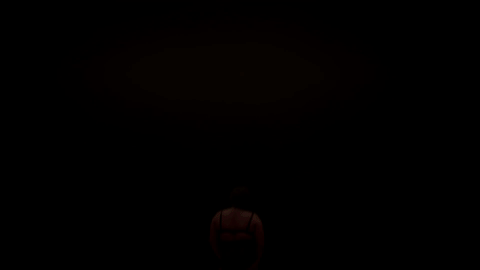
最後のヴォーギングはどう関係しているのでしょうか? 振付師/ダンサーのラッサンドラ・ニンジャ(Lasseindra Ninja)は、ヴォーギングのパイオニアです。ダンス集団ハウス・オブ・ニンジャとともに活動し、ヴォーギングをパリに持ち込みました。ヴォーギングは60年代のニューヨークで発展したダンススタイルです。黒人のクィアやLGBTコミュニティにとっては解放のダンスであり、正しい評価の獲得に向けた政治的活動であり、非常に重要なアクションでした。彼女に会う前は、ヴォーギングのボールルーム(コンテスト)で踊るダンサーたちは、ダンスを通して理想の自分を表現しているのだと、私は無邪気にも考えていました。しかしニンジャは、「そんなわけない」と私の考えを一蹴したのです。キャットウォークでの30秒程度のダンスタイムは、本当の自分となれる場が与えられる時間だと彼女は言っていました。ボールルームの外では別の人間にならなければいけない、社会の規範に即した役割を演じているのだ、と。
私はパリのさまざまなボールルームに足を運び、そこにすばらしい〈詩〉を見出しました。それぞれの会場が、あるテーマに沿って(例:ホラー映画)それぞれのハウスによって書かれた詩のようなものだと感じたのです。さまざまなカテゴリーがあり、ダンサーたちはテーマを自分なりに解釈して表現します。彼らは各カテゴリーのなかでテンションやリズム、構成のセンスを発揮し、対戦するのです。
ニンジャは、『Le Parfum de Cleopatre』というもう少し長いプロジェクトを発展させてこの作品を作り上げました。クレオパトラの香りによりダンサーたちが催眠状態になる、というアイデアをもとに膨らませた内容です。古代エジプトでは人間が神々に近づく術として香りが使われていました。香りは別の世界へとつながる扉だったのです。現在と過去、地上と天国。それをニンジャはこの作品のなかで表現しています。






