アルマ・ハレルはイスラエル系アメリカ人フィルムメイカー。彼女が織りなす官能的でドリーミーなストーリーは、想像と現実の間にある未開のスペースを探る。彼女のドキュメンタリー・フィルムメイキングは、溢れんばかりの感覚的刺激で、CHANEL Nº5 L’EAUの映像世界を築き上げた。彼女が光と音楽、踊りのうちに探る感覚的刺激は、実に濃厚で、風合いに満ちている。今回彼女がThe Fifth Senseのために作ってくれた『jellywolf』は、ファンタジーによって現実が霞み、抽象が具現の体験となり、溢れる色彩に空間が広がって浮き彫りになる感覚世界だ。ロサンゼルスの平凡なショッピングセンターに入居するオカルト感漂うショップを訪れたひとりの若い女性。彼女は、幻想体験を求めてやってきた。CHANEL Nº5 L’EAUのノートであるレモンとローズの香りを楽しむと、彼女は別世界へ―そこで目にするものは、まったく新しい体験だ。
劇中の若い女性が店で購入する体験は、この「共感覚」に触発されて思いついたという。
世の中には、強烈な心象を心に引き起こす香りというものがある。感覚が、遠い記憶と出会うのだ。共感覚を持つ人間は、様々な体験をする。たとえば、音を色として理解したり、香りをイメージとして理解したり——私の友人デクスターは、自らが共感覚の持ち主とは知らず、ある夜、ディナーの席で、「ホワイトハウスはケーキ、曜日は宙に浮かぶ円として感じる」と私に言った。「それは共感覚よ」と教えると、彼女はそれですべてが腑に落ちたようだった。「それは素晴らしいことなのよ。あなたの五感は、現実をクリエイティブに理解するためのライセンスを持っているの」
直感的にこのようなストーリーを思いついたのですか?
イメージや、無意識レベルの理論でものを考えるのが好きなんです。夢を監督するような感覚——それが映像作家として最大の挑戦ですね。高速でものを考え、自らの頭を混乱させたり意識を目覚めさせてしまわないよう注意しながら夢を監督しなければならない。夢では、信じられないようなことができます。感情を液体にしてそれを味わったり、現実とは違うジェンダーとして生きることもできる。そしてそれがリアルに感じる。今回のプロジェクトで私が挑戦したかったのは、私のロジックを映像で説明し、The Fifth Senseの世界の中で理路整然とそれを描くというものでした。
あなたの作品において、香りとはどんな重要性を持っているのでしょうか?
過去の物事や心の状態を思い出すために香りを用いたりします。香りをまとうことで、脳内に眠るとても複雑な存在の状態や感覚的記憶への道が出来上がったりするからです。俳優で同じことをする人も知っていますよ。ポジティブな記憶や、傷となった出来事の記憶を思い起こさせる特定の香りというものがあって、そういった感情をスクリーンに生むために香りを嗅いで演技に挑むんです。
感覚とは、小路を通じ直感へと繋がっていて、心を動かされるものや真実への憧れを思い出させてくれる。

私の世代は、アナログの時代に生まれ、今はデジタルの世界に浸っている。両方の感覚を持ち合わせているユニークな世代なんです。
映画監督だからこそ他の人とは違う感覚を体験するというようなことはありますか?
監督は五感が研ぎ澄まされていなければなりません。五感があってこその直感ですし、感覚があってこそ何に感動し、何をリアルに感じるかを思い出せるからです。元は感情の核の部分で作品作りをしていた監督が、クールだと“思う”ものや、周囲から期待されるものを作りに走ってしまうとき、私にはそれが分かってしまいます。気をつけなければ、簡単にそういう方向性へと流れてしまうものです。五感を使うことで、感情ときちんとコネクトした状態を保つことができますし、自分という存在が何たるかを思い出すことができます。
五感の中で特に重要だと感じる感覚は?
それはプロジェクトによります。最近は、コンセプトを絵に描くことですべての感覚を作品に織り込もうとしています。コンピューターだけでそれをやっても限界がありますからね。私の世代は、とても面白い世代だと思うんです。アナログの時代に生まれ、でも10代から20代にかけてデジタルの世界に取り込まれた世代ですからね。私たちはアナログとデジタル両方の感覚を得てここまできて、デジタルの意識をアイデンティティの一部として確立して大人になったわけです。私よりも前の世代の人々は、もっと歳をとってからデジタルの世界に巻き込まれたわけで、私の次の世代は完全なデジタル世界に生まれたわけです。そのインターセクションに育ったことをありがたく思うし、私の感性の多くはそこに端を発しています。私は完全にデジタルに染まってもいますが、同時にロマンチックなアナログのハートを持ってもいるんです。
映画学校で勉強をしたわけではないあなたのキャリアには、どんなプラスの出来事がありましたか?
誰からも「これが正しい」「これは間違っている」と言われることなく、自分の真の声というべきものを見つけることができました。私の人生や私という存在を何も知らない教師の言うことに惑わされずに済みましたね。「命令に従う能力がない」としてイスラエル軍から解放された私は、自ら選択して映画界の戦士になったのです。映画学校に通わなかったことで、感じるまま野性的にアートとコネクトすることができましたね。なんでも知っていると思っている人とは距離を置くようにしています。「どんなものも、答えはひとつじゃない」という視点で人から学び、歴史に敬意を評していきたいです。

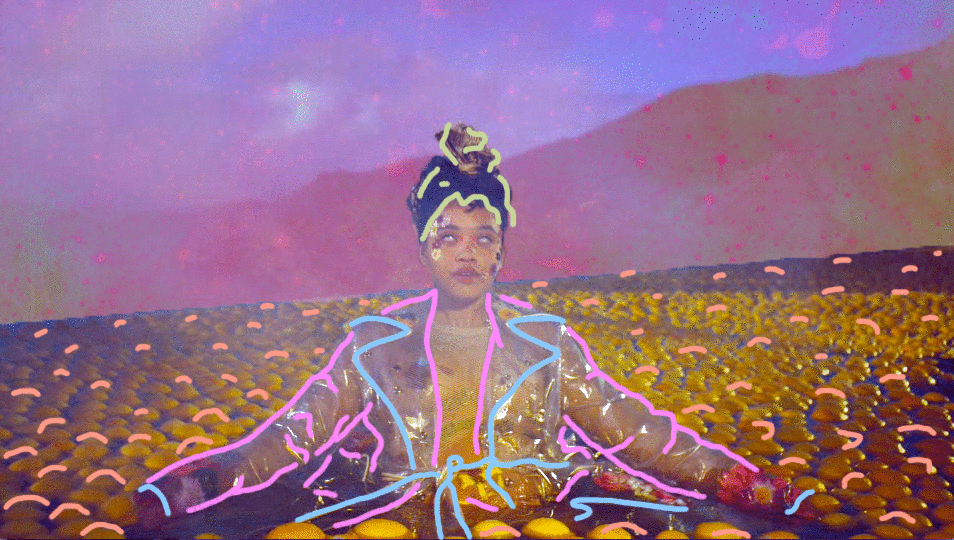
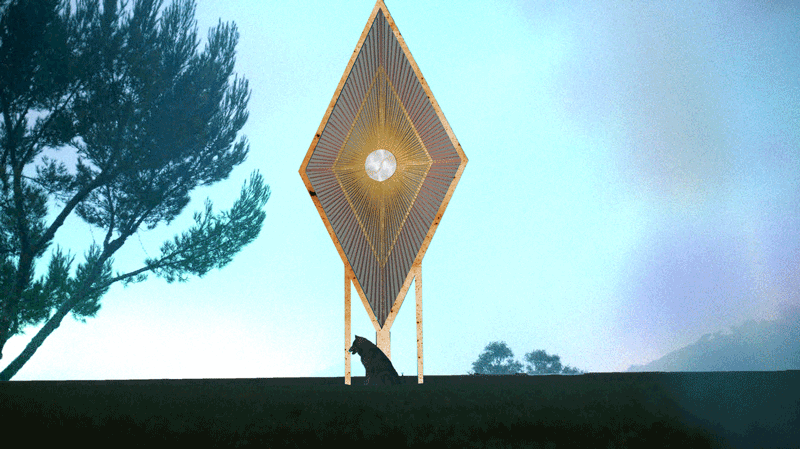

自分という存在にしか生み出せないものを作る上で基礎となる、「自分を知る」ということ——それをあなたは実地で学んだわけですが、だからこそ、自分のプロセスをコントロールする自由を得ることができたのでしょうか?
そうですね。しかしながらプロセスは常に変化するものです。たとえば、今回のプロジェクトのように、アイデアの半分は私自身のものでも、もう半分は与えられた条件に沿ったものでなくてはならない場合がある——今回はそれがCHANELという長い歴史と多大なる功績のある存在であるわけですが、こういう場合には特にプロセスが大きく変化します。学びの過程として、ひとつ何かを学べば、それは必然的に次の過程に影響してしまう——私はそう思うのです。私は、必要のないものは学べません。それを恥ずかしく思った時期もありました。学校ではいつも試験で悪い成績ばかり取っていたし、そのおかげで高校も卒業していませんからね。学習能力に欠けているわけですが、それから時間をかけて、自分の脳がどのような情報に反応を示すか、何に疑問を感じるかを理解しました。
イスラエルに育ったということは、あなたが物語を作り上げる手法に何かしらの影響を与えているのでしょうか?
イスラエルは、相反する要素に溢れた場所です。現実を捉えるということにおいて、私はイスラエルで育ったことであらゆるものを公平に並列して見るということの意味と価値を学んだと思います。
それが、あなたの作品で言葉というものが主たる力を与えられていない所以なのでしょうか?
そうです。人生においてもっとも大切なことは、言葉では言い表せませんから。
映画学校に行かなかったおかげで、誰にも邪魔されずに自分のオリジナルを見つけることができた。









ストーリーやアイデアを探しているときにどんなコネクションを感じますか?
移民としてアメリカに生きているという現在と、中東で育ったという過去を持つ私は、これまで常に、アイデンティティのため、愛する権利のため、そして愛される権利のために、苦悩し戦う人々のストーリーに惹かれ続けてきました。
また、「ひとは誰も仮面をまとって生きているんだ」という概念にも強く惹かれます。とてもシンボリックな視点だと思うんです。私たちには頭骨があり、その中に脳というものを持っている——顔とは、それを覆う仮面のようなものだ、と。仮面としての顔の存在に気づかせてくれ、そこに私たち自身の姿を見出せるストーリー——それを見ることで、私たちがもっとそれぞれのアイデンティティに悩むことなく生きることができ、愛をもってお互いを見つめ合えるような、そんなストーリーに興味があるんです。世の中には、その顔の部分だけを讃えるストーリーが多すぎます。私たち人間が皆でイマジネーションと夢を共有すれば、私たちは自らを解放することができる——私はそう信じています。だから、私は精神や現実の捉え方を捻じ曲げ、変えていこうと努めています。
起用した人々やストーリーはどのようにして見つけたのですか?
運命はキャスティング・ディレクターです。2011年に作った『Bombay Beach』と2017年の『LoveTrue』では、ピンとくるキャストを見つけるために知らない場所を歩きまわりました。探し求める存在を見つけるために、実際にその場所に行って歩いたり車を走らせたりしなければならない——私はそういう映画監督なのです。恋に落ちるのと似ています。ただ、これはカメラを通しての恋で、カメラには独自の“惹かれるルール”のようなものがあるのです。
Soft as jelly, Wild as Wolf

It's time to glow in the dark together
それは、探している自分とはまた別の次元で起こる体験なのでしょうか?
そうですね。大統領就任式の翌日、私はウィメンズ・マーチに参加して、迷子になりました。寒すぎて、携帯電話の充電は切れてしまったのです。群集の間を縫って歩きまわり、どうやったらバックステージにたどり着けるかを考えました。その時、突然、周りにいた数人の女性が歌い始めたんです。それを映像に収めたいと思い携帯電話を取り出して見ると、電源が切れてしまっていたはずの携帯電話が突如息を吹き返しました。歌を歌う女性たちを映像に収めながら、その歌詞に胸を打たれました。「I can’t keep quiet.(黙ってはいられない)」と彼女たちは歌っていたのです。涙が溢れてきて、私は彼女たちから離れました。その夜、ロサンゼルスに帰る飛行機の中で、日中に携帯電話で録画した映像をYouTubeにアップロードしたんですが、その映像はアップから3日間で1,500万回のビュー数を記録し、世界中の女性たちが、その歌を「ウィメンズ・マーチのアンセム」と呼ぶようになりました。あの映像は、これまでの2作で私に起こったことを濃縮させたものだと感じます。自分を未知の空間に投げ入れてしまうということ、自分の奥底にある柔らかい部分に触れる人々と出会うということ、そしてそんな人々のストーリーを伝え、そのストーリーを必要としている人々に届けるということ。
『LoveTrue』で歌を歌ってくれているストリート・ミュージシャンのヴィクトリー(Victory)は、ジェイ・Zのレーベル、RocNationに見出されて、契約にまで至ったんですよ。ジェイ・Zが『LoveTrue』を観てくれたことがきっかけだったそうです。ヴィクトリーの歌には、多くの人に重要な意味をもって響くメッセージがあると私は思います。
感情的にも精神的にも、私は被写体に惚れ込み、惹かれていなければ、映画など撮れません。愛と関係に根付いたものでなければならないんです。そうでなくても映画が撮れる監督だったらどんなに良かっただろうと思うこともありますが、やはり私は愛と関係を基礎とした映画作りしかできないんです。




フラッシュバックや想像シーンを織り交ぜ、また俳優を起用するなどするあなたの作品は、これまでに「ドキュメンタリーに革新的で新鮮な風を吹き込んだ」と称されてきました。そのようにストーリーを伝えようと決めた経緯は?
ただそれらの手法に興味があったのと、自分のフィルムメイキングに何も規制を設けなかったことで、自然とそのような手法が生まれたんです。2001年に『Bombay Beach』がリリースされたとき、ドキュメンタリー・フィルムメイキングの新たな時代が幕を開けました。ソルトン湖を囲む3つの郡はカリフォルニア州の中でももっとも貧困が厳しい地域ですが、私は「振り付けされたダンスを通してそれら地域に生きる人々のストーリーを伝えよう」と思いました。映画に出てくる人々はダンサーではなく、ダンスと何の関連も持たずに暮らしている人々でした。その一年前に、クリーオ・バーナード(Clio Barnard)監督が『The Arbor』という映画で俳優たちとリップシンクのサウンドを用いて、劇作家の故アンドレア・ダンバー(Andrea Dunbar)の悲劇を描いていましたし、他にも既存の手法からフィルムメイカーたちを解き放ってくれるようなクリエイティブなドキュメンタリー作品がたくさん生まれていました。今になって当時を振り返ると、あの頃にドキュメンタリー・フィルムメイキングが新たな方向性に舵を切ったのだとわかります。当時は、「実話を伝える手法」としてのドキュメンタリーについて、大きな議論が巻き起こっていたんです。そういった新たな手法に「騙されている」と感じる人も少なくなかった——批判していた人たちは、フィルムメイカーにとっての真実性には目を向けず、フィルムメイキングの手法にばかり固執していました。堅苦しいジャーナリスティックな視点から現実を見つめるというアプローチと、作品に浮かぶ“詩的な真実”とやらを、フィルムメイカーの意図よりも優先してしか考えられない人たちだったんです。
それに対するあなたの答えは?
壁にとまったハエのようにただ現実を見つめる視点なんてどうでもいい——私は部屋に入り込んだゾウよ、と。要は、「ドキュメンタリーとはいえ、私たちが映画を作っているという事実から免れることは絶対にできないし、どうせ作るのなら私はそれをアーティスティックにしたい、そして出演してくれる人たちをよく知り、彼らとのアーティスティックなコラボレーションで作り上げたものにしたいのよ」ということです。そこに何を見出すかは観客によって違うわけですし、観客はフィルムメイカーの手法をベースにして作品に何かを見出すわけではないのです。観客は、作品を通して与えられた要素をベースとして、そこに色々なものを見出すのです。実のところ、ドキュメンタリーとは常にそうやって作られてきたものなんです——多かれ少なかれ、操作されているものなのです。ニュースも同じですよ。現代は、誰でも映画を作ることができるし、ニュースを報じることもできる。そういう世の中だからこそ、私たち現代人は映像ににじみ出る「意図」を見ることに長けている。「意図こそが大切なんだ」と多くの人が感じているのです。こういうストーリーを伝えることを私は重要だと考えています。作品を観てくれる人たちに、作中の虚構の真実を受け止め、それをリアルなものとして信じ、自身にとっての真実についてよく考えてもらいたいからです。また、私の被写体には堂々とそれぞれのストーリーを語ってもらいたいです。
香りには、男性の価値観に左右されないフェミニンな神秘さがある。Jelly Wolfでは、これを表現したかった。
Episode 4
私は思いのままに夢をコントロールできる。素早く考えを巡らしながら、あわてて目覚めないよう気を配り、自分の思うように夢を描く。これは私の作家として究極へのチャレンジなんです。
音楽はあなたのフィルムメイキングにおいて重要な鍵を握る要素だと思いますが、特定の音楽を念頭において映画を作るのでしょうか? それとも映像が完成してから音楽を決めるのでしょうか? そしてどのように音楽とイメージの調和を映像に生むのでしょうか?
ミュージシャンの友達は私がやることなすことすべてにおいて大きな意味と役割を担っています。映画のプロジェクトを進める際には、可能な限り初期の段階で彼らを巻き込みます。たまに、知らないミュージシャンに夢中になり、今後の作品で一緒に何かできるかもしれないと感じることがあります。『LoveTrue』を作ったときには、フライング・ロータス(Flying Lotus)を追いかけ回し、ようやく一年経って彼との繋がりを築けました。私が色々とトライしてうまくいかなかったことも、彼の音楽のおかげで全てが丸くまとまりました。私のキャリア初期、まだVJとして活動していた頃は、映像のループをカットして繋ぎ合わせてビデオ・アートを作り、コンサートやクラブでミュージシャンたちとともにステージで映像をプレイしたりしました。映像を楽器としてバンドの一員になりたいと思ったものです。あの頃、観客を前に生で映像をプレイした経験が、イメージの音楽的性質との特別なコネクションを育んでくれたんだと思います。
あなたは作品で日常とファンタジーを織り交ぜますが、そのように相反する要素を並列する手法に関して思い出せるもっとも古い記憶は?
私が3歳の頃、まだテルアビブに暮らしていたとき、父が母のパンティストッキングを履いて裸でリビングのテーブルに乗り、踊っていたのを覚えています。父はとても男らしい人で、でもあの時はかなり酔っ払っていました。大きな音で音楽をかけて踊っている父に、私と母は大笑いしました。もちろん、ご存知の通りあの時代のあの地域は笑いが絶えない状態などどの家庭にもありませんでした。しかし、病んでいると思われるでしょうが、たまに訪れるああいう瞬間が人生に魔法のような時間とオープンな雰囲気をもたらしてくれました。子供時代に痛みを経験していると、あのような魔法の瞬間というのはずっと胸に残るものです。12歳の時、父に「またあれやって」と頼み、映像に収めました。おそらくあれが私にとっては初めての映像作品です。
そのイメージがずっと胸にあるわけですね。
そうだと思います。私が初めて作った映画には、大人の男が踊るシーンがありますからね。そして、踊ってくれた男のうち二人は完全に酔っ払っていました。アートが持つ美しいセラピー効果とでも言いましょうか。今の今まで、そこのコネクションについて考えたことはありませんでした。
最後に、The Fifth Senseの読者へメッセージをお願いします。この作品を観て、どういったことを感じてもらいたいですか?
これは全女性に宛てた奇抜なラブレターです。香りが持つ不思議な感覚を捉えるとともに、目を背けたくなるような記憶にコネクトすることで生まれる、解放された女性のアイデンティティを捉えようと努めました。私と同様の精神を持った人々の心に響く作品——それが私の作品の魅力だと思っています。自分が育った環境から遠く離れた土地に暮らし、話したこともないひとが、自分の作品に何か深いものを感じ取ってくれる——共通した体験があるわけでもないのに、私の作品に共鳴してくれる。それほど嬉しいことはありません。しかし、結局のところ、私は使命感に駆られて作品を作っています。私が狂わず、幸せでいられるのは、映画作りがあるからです。


